- 一、学術調査の概要
- 二、上海博物館
- 三、武漢大学簡帛研究中心・長沙簡牘博物館
- 四、岳麓秦簡
- 五、湖南省文物考古研究所
三、武漢大学簡帛研究中心・長沙簡牘博物館

武漢大学簡帛研究中心の会議室にて
八月二十九日、我々一行は、武漢大学簡帛研究中心を訪問し、李天虹教授・劉国勝教授・宋華強副教授との座談会を行った。
まず簡帛研究中心が現在取り組んでいる研究プロジェクトについて尋ねたところ、以下の三つとの回答であった。第一に、当日不在でお会いできなかった陳偉教授を中心とする、秦簡の総合研究である。これは、発表済みの秦簡の研究成果を集めて整理し、赤外線写真の撮影を含めた竹簡の図版の整理を行うものである。第二に、李天虹教授を中心とする、湖北省から出土した未公開の五種類の楚簡(江陵藤店・老河口市安崗・江陵磚瓦廠・江夏丁家咀・荊門厳倉から出土したもの。内容は遣策と占卜関係)の整理である。第三に、新聞出版総署の「中華字庫」プロジェクトである。これは、中国の古代から清代までの漢字や少数民族の文字をすべてデジタル化するもので、簡帛研究中心は主に秦代の簡牘の文字について担当する。三つのプロジェクトは、いずれも簡帛研究中心が団体として参加するものであり、それぞれの教員はこれらとは別に、個人として取り組むプロジェクトや研究課題があるため、皆とても忙しい、とのことであった。
続けて、李教授を中心としている厳倉楚簡の整理の進捗状況について質問した。李教授は、「二〇一〇年に出土した厳倉楚簡については、出土した時点で竹簡の写真を現場で撮影し、簡単な釈文を作成した。現在は写真に基づいて釈文の修正を進めるとともに、赤外線写真の撮影を行っている。整理作業の終了時期はは二〇一三年の年末の予定である。厳倉楚簡はすべて残簡で、完簡はなく、復元はほぼ不可能である。全体の文字量は二百字程度、簡長は六十~七十㎝、盗掘を受けているため他に出土した器物はない。厳倉楚簡は墓主が確定されており、墓主は「悼滑」である、この人物については伝世文献にも記載がある。墓主が判明することは珍しい」と回答された。
また、中国各地では近年も出土が続いているのかと質問したところ、「最近荊州から数枚の楚簡(内容は文書)が出土した。湖北省では他にも未発表の出土資料がある。それらについて考古的調査は行っているが、出版には至っていない。七〇年代に出土した藤店の竹簡は肉眼では文字を読み取ることができないが、赤外線ではよく見えた」との回答があった。
さらに我々は、劃痕に関して意見をうかがった。これに対する李教授の回答は、以下の通りである。
最も古くには、包山楚簡の報告書に劃痕に関する言及がある。或る劃痕は竹簡の配列を示す手がかりになるように思われるが、必ずしもすべての劃痕がそうではないため、これまでほとんど注目されることがなく、写真もほとんど残されなかった。上博楚簡にも劃痕はあるかも知れないが、当初はその存在に気付かなかったため、写真はない。脱水後は劃痕が判別しにくくなった。厳倉楚簡にも劃痕のような線が見えたが、鮮明な写真を撮ることができず、さほど注目してはいなかった。二〇一一年に再度調査し、竹簡の背面を赤外線で写真撮影した結果、劃痕のあるものが十~二十枚確認できた。しかし、厳倉楚簡は残欠が激しく、竹簡の配列を復元することは困難である。
二〇一〇年に『清華大学蔵戦国竹簡(一)』が刊行され、竹簡背面の写真がすべて公開された。当初は清華大学も竹簡背面の竹簡番号(ノンブルに当たるもの)だけに注目しており、劃痕には注目していなかったようだ。
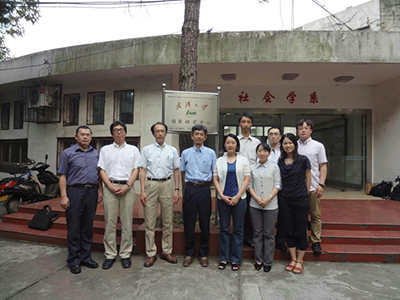
武漢大学簡帛研究中心のある建物の前にて
私(李)は竹簡背面の写真を見て、竹簡背面の線の重要性に改めて気付いて、簡帛網に小さなニュースを発表した。その後二〇一一年に清華大で竹簡の形制に関する報告をした際、その文章の中で劃痕に触れた(清華大学出土文献与保護中心主催の「清華大学蔵戦国竹簡(壹)国際学術研討会」を指す。二〇一一年六月二十九日)。その発表に対する反応はかなり良かった。この清華大での会議で、多くの人が劃痕の問題に興味を持ったようである。北大簡の劃痕については、その後孫沛陽氏が、未発表の資料に基づくものであるが、論文を発表した(「簡冊背劃線初探」を指す。『出土文献与古文字研究』第四輯所収、二〇一一年十二月)。私も劃線についての論文「湖北出土楚簡(五種)格式初析」(『江漢考古』二〇一一年第四期(総第一二一期)、二〇一一年十二月)を発表した。
岳麓書院蔵の秦簡の背面にも劃痕はあり、こうした劃痕について学界では、劃痕は編連のためであり、竹簡の配列の復元に役立つという見方が主流であるが、私は劃痕についてまだはっきりしたことを確定することはできないと考えている。劃痕が参考になることは間違いないが、竹簡の編連と直接的な関連を持つものであるかどうかについては、疑問を感じている。今後劃痕と関連のある竹簡背面の写真はすべて公開されるようになるであろうから、将来、十分な資料に基づいて、自然に結論が出てくるのではないか。現在は、急いで結論を出すべきではないと考える。
以上の李教授の回答に続き、劉教授が李教授の意見に賛成する立場から、劃痕に関する問題は、まず第一に竹簡の編連との先後関係についてであり、第二に誰が劃痕を残したのかという点についてであるとし、包山楚簡の大部分(二~三枚を除く)には劃痕はなく、郭店楚簡にも無いと指摘した。
宋副教授も、劃痕の作者は誰か、その目的は何かという点が問題である、劃痕は文献の形成に関わる重要な情報であると思うが、この問題の解明には更なる資料が必要である、劃痕による竹簡の配列の復元について過大に評価することはできない、自分は北大漢簡を見たことがあるが、劃痕のあるものもあり、ないものもある、竹簡の編連を文字を根拠として行った場合、正面の文字と背面の劃痕との対応が良くないことがある、と述べられた。
なお、この二日後の八月三十一日、我々一行は長沙簡牘博物館において、赤外線スキャンした画像の処理をパソコンで行っている作業や釈文作成作業の見学を行った。この時我々に対応してくださったのは元館長の宋少華教授である。我々は宋教授にも劃痕に関する質問をして、回答を得たので、紹介しておく。

長沙簡牘博物館の整理室にて。左から三人目が宋少華教授。
宋教授に対する質問は、長沙簡牘博物館が行っている簡牘の撮影や釈文作成においても劃痕に注目しているか、というものであった。これに対する宋教授の回答は以下の通りである。
すでに我々は簡牘の背面にある文字以外の情報についても注意して観察しており、昨年考古研究所が発掘した後漢の竹簡の背面に劃痕があることを確認した。竹簡の状況から、まず書写が行われていない竹簡を配列して、その竹簡の背面に線を記した後、次いで書写を行い、続いて竹簡の編聯を行った、と考えている。但し、清華簡の場合は竹簡背面に線が記されているが、この後漢の竹簡の場合は、竹簡背面の表面がナイフなどの何か堅いもので傷つけられていた。なお、木牘についてもその背面に線がある場合があり、劃痕に基づいてそれの配列を復原することができる。そうした現象は、長沙簡牘博物館が所蔵する三国呉簡と漢簡とには見られないが、編聯された行政文書の木牘数枚の背面に、劃痕がクロスして記されているものを見たことがある。
前章で述べた上海博物館に加えて、この武漢大学簡帛研究中心や長沙簡牘博物館での調査により、我々は劃痕に関する研究の情況について、大いに理解を深めることができた。二〇〇九年に北京大学が入手した漢簡において劃痕が発見されたことや、二〇一〇年に刊行された『清華大学蔵戦国竹簡(一)』に竹簡背面の写真が収録されたことなどを契機として、出土文献の研究に携わる研究者の間で劃痕に対する関心が急速に高まり、その研究が進み始めているのである。もっとも、李教授が指摘する通り、北京大学の漢簡をはじめ、劃痕に関する重要な資料は、ほとんどがまだ公開されていないのが実情である。このため、劃痕とはそもそも如何なるものかといった基礎的な点を含めて、研究者の間で認識が十分共有されるに至っていないように思われる。
果たして劃痕は、出土した簡牘の配列の問題を解明する手掛かりとして有効なのか。有効であるとするならば、どの程度有効なのか。こうした点は、今後出土文献研究において大いに注目される研究課題の一つといえよう。
(竹田健二)
 中国出土文献研究会
中国出土文献研究会